真言宗豊山派
補陀洛山善明院歓喜寺
| ●遍 照 金 剛 弘 法 大 師(へんじようこんごうこうぼうだいし) 空(くう) 海(かい) 大
和 上(だいわじよう)
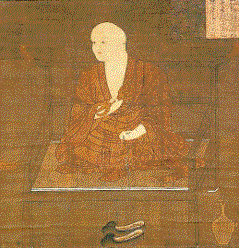
空海大和上は平安時代の僧。日本の真言宗の開祖。諡(いみな)は弘法大師。灌(かん)頂(じよう)
名(めい)は遍照金剛(へんじようこんごう)。天台の最(さい)澄(ちよう)と並ぶ平安仏教の創設者。
讃岐の人。俗姓佐(さ)伯(えき)氏。十五歳で母方の伯父阿刀大足(あとのおおたり)について京都へ
遊学。儒学などを修め、十八歳の時『三教指帰(さんごうしいき)』の原本を著し仏道に入る。勤操
大徳(ごんぞうだいとこ)について南都仏教を学び、次いで国内の難所で修行。八〇四年入唐。長安
で青(せい)竜(りゆう)寺(じ)恵果大和尚(けいかだいかしよう)につき密教の奥義修得。三年後帰
国。高野山、東寺を密教の根本道場とし、各地を巡歴。東大寺別当を兼ね綜(しゆ)芸(げい)種(し
ゆ)智(ち)院(いん)を創設、真言密教を宗派として確立した。その教義は『弁顕密二教論(べんけん
みつにきようろん)』『十(じゆう)住(じゆう)心(しん)論(ろん)』などに、その文学は『性(しよう)
霊(りよう)集(しゆう)』『文(ぶん)鏡(きよう)秘(ひ)府(ふ)論(ろん)』などに著され、書において
は三筆の一人で『風(ふう)信(しん)帖(じよう)』『灌(かん)頂(じよう)歴(れき)名(めい)』などは
至宝とされている。
● 真(しん) 言(ごん) 宗(しゆう)
金剛界・胎蔵界 曼荼羅
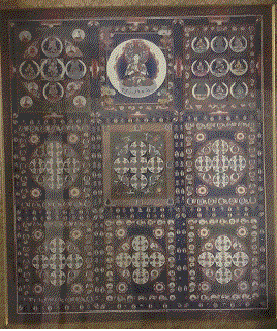 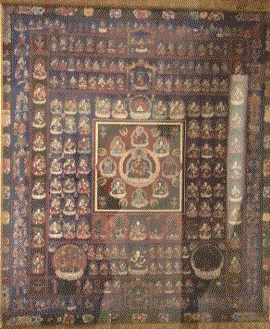
真言宗は大(だい)乗(じよう)仏(ぶつ)教(きよう)中の密(みつ)教(きよう)の日本での一派。中国
密教を空海が八〇六年に伝え,八一六年金(こん)剛(ごう)峯(ぶ)寺(じ)開創のころ宗派として独立
した。密教の伝統はインドの金剛薩?(こんごうさつた)が大(だい)日(にち)如(によ)来(らい)(本
尊)の教えを受け継ぎ、竜猛菩薩(りゆうみようぼさつ)(龍樹菩薩)・金剛智三蔵(こんごうちさん
ぞう)を経て中国に伝わり、不空三蔵(ふくうさんぞう)・恵果大和尚(けいかだいかしよう)を経て空
海大和上に伝わった。根本経典は『大日経(だいにちきよう)』と『金剛頂経(こんごうちようぎよ
う)』。教義は人間の日常の言語的概念を離れ、真言(サンスクリットのマントラ mantraや陀(だ)
羅(ら)尼(に)を仏の真実のヒビキとし)を直接感受することを重視し、金胎両部(こんたいりよう
ぶ)の曼(まん)荼(だ)羅(ら)を建て、即(そく)身(しん)成(じよう)仏(ぶつ)(この身このままで仏と
して生きること)が本旨である。 空海は金剛峯寺と教(きよう)王(おう)護(ご)国(こく)寺
(じ)(東寺)を根本道場とし(東密)、平安時代を通じて教勢は振るい、教理、儀式、仏教芸術に
おける各方面への影響は大きかった。 平安末期に覚鑁上人(かくばんしように
ん)が自性加持身説(じしようかじしんせつ)を唱えて、高野山・東寺側と分裂し、新義真言宗が生れ
た。これは後に真言宗豊山派(ぶざんは)(長(は)谷(せ)寺(でら))と真言宗智(ち)山(さん)派(は)
(智(ち)積(しやく)院(いん))に分かれた。新義真言宗に対し従来のものを古義真言宗と称し、高
野山真言宗、真言宗山(やま)階(しな)派、真言宗醍(だい)醐(ご)派、真言宗御(お)室(むろ)派、真
言宗泉(せん)涌(にゆう)寺(じ)派など約三〇派に分かれる。
● 新(しん) 義(ぎ) 真(しん) 言(ごん) 宗(しゆう)
従来の真言宗を古義真言宗というのに対し、新義派を形成して、新義真言宗という。
興教大師覚鑁上人(こうぎようだいしかくばんしようにん)を祖とする豊山 、智山の両派をいう。
覚鑁上人は保延六 (一一四〇) 年に高野山東寺派の真言宗の主張している大日如来本(ほん)地(じ)
法(ほつ)身(しん)説(せつ)に対し、
自性加持身説(じしようかじしんせつ)を唱えたため分裂し、和歌山県根(ね)来(ごろ)に退いて一
(いち)乗(じよう)山(ざん)円(えん)明(みよう)寺(じ)を開創した。正応十一(一二八八) 年に覚鑁上
人の血(けち)脈(みやく)を受けている頼瑜僧正(らいゆそうじよう)は、弟子を率いて高野山に帰っ
たが、再び弟子とともに退いて根(ね)来(ごろ)寺(じ)を建立した。これにより、完全な分裂とな
り、新義真言宗が独立した。根来の法流は、のちに奈良長谷寺の専(せん)誉(によ)僧(そう)正(じよ
う)と、京都智積院の玄(げん)有(ゆう)僧(そう)正(じよう)に伝わる。前者を豊山派、後者を智山派
と呼ぶ。
● 真言宗 豊山派
補陀落山 善明院 歓喜寺
沿革
宗 旨:新義真言宗
宗 祖:遍照金剛弘法大師空海
中興祖:興教大師覚鑁
派 祖:小池坊(こいけのぼう)専(せん)誉(によ)僧正
真言宗豊山派
新義真言宗の総本山根来寺は室町時代末期の最盛期には、坊舎四五〇(一説には二七〇〇)を数
え一大宗教都市を形成し、寺領七二万石を超えていた。根(ね)来(ごろ)衆(しゆう)とよばれる僧衆
(僧兵)1万余の一大軍団を擁していた。また、根来寺僧によって種(たね)子(が)島(しま)から伝来
したばかりの火縄銃一挺が持ち帰られ、僧衆による鉄砲隊が作られた。この拡大勢力に脅威を感じ
た豊臣秀吉は何度か解散を促したが、高野山は従ったものの、根来衆は全く応じなかった。秀吉は
学侶(出家学問僧)を密かに山から逃がした上で、根来寺に総攻撃を加え、衆徒の老若何女を問わ
ず殲(せん)滅(めつ)した。 根来寺を追われた専誉僧正が豊(とよ)臣(とみ)秀(ひで)長(なが)公に
保護され長(は)谷(せ)寺(でら)に招き入れられ、ここで真言宗豊山派が形成された。 この
長谷寺には、専誉僧正を慕う、我が国最高峰の碩学僧侶(学侶)達三〇〇〇人が集結する学山とな
った。
豊山maru 派の派名は長谷寺の山号「豊山(ぶさん)」に由来する。
●総(そう)本(ほん)山(ざん) 長(は)谷(せ)寺(でら)
新義真言宗 総本山 豊山(ぶさん) 神(かぐ)楽(ら)院(いん) 長(は)谷(せ)寺(でら)
奈良県桜井市初瀬七三一-一
寺伝によれば、天武朝の朱鳥(あかみどり)元年(六八六年)、僧の道明(どうみよう)上人が初(は
つ)瀬(せ)山(さん)の西の丘(現在、本長谷寺(もとはせでら)と呼ばれている場所)に三重塔(さん
じゆうのとう)を建立、続いて神(じん)亀(き)四年(七二七年)、僧の徳(とく)道(どう)上人が東の
丘(現在の本堂の地)に本尊十一面観音像を祀って開山した。
東(とう)大(だい)寺(じ)(華(け)厳(ごん)宗(しゆう))の末寺であったが、平安時代中期には興
(こう)福(ふく)寺(じ)(法相宗(ほつそうしゆう))の末寺となり、十六世紀以降は覚鑁上人(興教
大師)によって興され頼瑜僧正により成道した新義真言宗の流れをくむ真言宗豊山派の総本山とな
った。
● 真 言 宗 豊 山 派
金(こん)剛(ごう)山(さん) 長谷寺(ちようこくじ)(保原)
福島県伊達郡保原町五丁目三十
江戸期、幕府の寺院本末制度の施策により、新義真言宗の中本寺となった陸奥國伊達郡保原中村
の長谷寺は、もともと、この辺りの真言宗醍(だい)醐(ご)報(ほう)恩(おん)院(いん)の法流を汲む
寺の中心であった。幕府の施策により伊達西根、東根六十六郷、小手の庄二十一郷、信夫郡にまで
及ぶ新義真言宗の寺院を統括する「本郡本寺」となった。
※江戸幕府統制期における信達地方の新義真言宗の寺院は、
◆本寺保原「長谷寺」(醍醐報恩院法流)
末寺十一ヶ寺、門(もん)徒(と)二十一ヶ寺。◆本寺福島「真浄院(しんじよういん)」 (江戸の
彌勒寺(みろくじ)の法流)
末寺七ヶ寺、門徒(大福寺門徒)十五ヶ寺と別門徒一ヶ寺の一派。◆本寺伊達郡八幡「亀(かめ)
岡(おか)寺(でら)」(和州小池坊総本山長(は)谷(せ)寺(でら)の直(じき)末(まつ)寺(じ)、亀(か
め)岡(おか)八(はち)幡(まん)宮(ぐう)の別(べつ)当(とう))末寺一ヶ寺。
これらは寛政七年の江戸幕府編纂の『寺院本末帳』に記録されている。なお、このとき、歓喜寺
は末寺第七番目に記録されている。
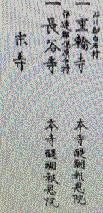 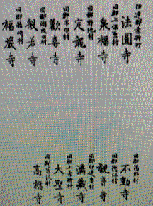 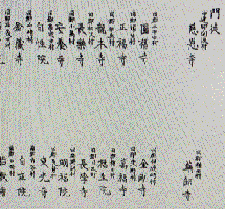
寛政七年
●明治期に寺院本末制度は廃止された。更に、各地で、激しい廃(はい)仏(ぶつ)毀(き)釈(しや
く)運動が起こり、廃寺に追い込まれた寺も多い。しかし、この辺りの新義真言宗の各寺院は奈良県
桜井市の長谷寺を本寺としながら、各寺院の存続をはかった。 やがて、昭和二十七年宗教法人法
施行により、これらの寺院は真言宗豊山派を包括宗教法人とする被包括宗教法人として認可を得
て、現在に至る。この中には、事情により、一部の寺院が真言宗豊山派から離脱し、新義真言宗室
(むろ)生(お)寺(じ)派(は)に転派している寺院もある。※本郡本寺の保原長谷寺は、火災で、歴史
資料のほとんどは消失。 |
|
|

|