真言宗豊山派
補陀洛山善明院歓喜寺
| 補 陀 落 山 善 明 院 歓 喜 寺 年表
●寛永元年(一六二四)西根上堰着工。完成後開墾により移住者が多くなる。更に、幕府の寺院本
末制度によって、各寺や檀家を幕府が管理する時代に入って、それまで、氏(うじ)寺(でら)・一檀
(だん)那(な)寺(でら)として創建されていた歓喜寺も、制度上、地域における寺の役割が確立でき
なければ、寺院存続寺自体が危ぶまれることになった。それは、従来の氏寺のみならず、地域住民
の掌握に資する菩提寺としての機能を果たさなければ、寺院として、幕府に認められることはない
という厳しいものであった。
それゆえ、寛永二年(一六二五)に大聖寺(伊達崎)を開山した法印宥甚大和上を歓喜寺の住職
に委嘱し、村内の「坊ノ内」、「西正寺」の地にあった熊野山等の諸堂を歓喜寺に統合し、「補陀
落山善明院歓喜寺」として、幕府の認可を得るよう手続きをとり寺の再興をはかったと思われる。
●寛永十年(一六三三)二月十二日に、ようやく、体制が整うことによって、歓喜寺は宥甚大和上
を中興開山として、保原の長谷寺末寺となるべく準備されたと思量される。寺院に檀信徒「過去
帳」を常備し、寺檀挙げて、この寺を護った。寺の住職についても、保原の本寺長谷寺の法流を継
ぐ僧侶によって引き継がれる体制になった。
(実際には、幕府の『寺(じ)院(いん)本(ほん)末(まつ)帳(ちよう)』陸奥国新義真言宗本末帳
(寺院本末帳五十七)によると、寛政七年(一七九五)十二月、幕府にようやく提出されている)
●寛永十年 西根上堰完成
●慶安二年(一六四九)二月七日当寺中興開山、法印宥甚 遷化。
※註「中(ちゆう)興(こう)」とは、寺院を再興隆すること。
※註「開(かい)山(さん)」とは、創設された寺院の基盤を盤石にすることや、衰微した寺院を新
たに再興したことをいう。
歓喜寺は歴史上、幾たびか衰退の憂き目に遭いながらも、何度も復興し、今日まで受け継がれて
いる。その時の並々ならない功績を称え、「中(ちゆう)興(こう)開(かい)山(さん)」と称していま
す。
※註「遷(せん)化(げ)」とは、高僧が亡くなること。
●「元禄四年(一六九一)六月二日卒 開基旦那 稲村清左衛門道清
中興開山祐雄法印代、稲村清左衛門道清、寺院再興に貢献、開祖旦那となる。
※註「開(かい)基(き)」とは、寺院を創建し、基盤を築いた僧を「開基」という。また、寺院の
創建のために多大な貢献をした大檀那施主を「開(かい)基(き)檀(だん)那(な)」という。
●「享保元年(一七一六)七月二十六日当寺中興開山、法印祐雄」
●「宝暦元年(一七五一)十二月十八日 實道和尚代
●宝暦二年(一七五二)當山第一世實道上人三世宥栄上人並稲村清左衛門(朝成)等協議 によ
り、歓喜寺再興を祈念して鐘撞堂兼山門及び梵鐘鋳造建立。」
●「宝暦五年(一七五五)十月十八日 遍照院實道和尚位 定法流 第一世当寺法流元祖 遷化」
●「天明二年(一七八二)八月 宥栄和尚代
●天明二年(一七八二)十一月十三日 遍照院宥栄和尚位 定法流 第三世当寺法流元祖 遷化」
註記:【「法(ほう)流(りゆう)」とは、住職となる僧侶が阿闍梨や師匠から受け継いでいる真言
宗の厳密な法流で、「血(けち)脈(みやく)」や「印(いん)信(じん)」という「証(しよう)文(も
ん)」が極めて重要である。また、この法流は檀徒が亡くなった際に、住職から亡くなった御精霊に
お授けされる最重要な「受(じゆ)戒(かい)」・「引(いん)導(どう)」の「血(けち)脈(みやく)」の
根幹となっているものである。
ただ、真言密教は阿闍梨から弟子への傳受であるため、寺の住職であっても、寺の法流よりも僧
侶自身の法流によらざるを得ないものである。このことから、しばしば、幕府によって規制された
「宗派の法流」と「寺の法流」と「住職自身の法流」は一致しないことがある。この場合、阿闍梨
位である住職の法流が優先される。例えば、古くからこの辺りの法流が古義真言宗の醍醐報恩院の
法流を汲む僧によって継承されている寺の実態があった。近年まで保原の本地長谷寺もその末寺も
醍醐報恩院流の幸心方を底流にしていたのは師匠から弟子へ法流が受け継がれるものであるからで
ある。現在は豊山派の寺は全て、寺も僧侶もみな新義真言宗の大(だい)伝(でん)法(ぽう)院(いん)
流(りゆう)となっている。
●「文政十二年(一八二六)二月宥政法印 正徳寺本尊阿弥陀如来坐像安置」
●「天保十一年(一八四〇)九月宥政法印 この地方の守護のため歓喜寺から菩薩の仏像一体を銀
山坑口に近い愛宕山に納め祀る。」(愛宕神社)
●「明治十年(一八七七)九月 祐?代 本堂、庫裏 再建
●「昭和十七年一九四二)十一月祐覚代 梵鐘供出
●昭和四十九年十一月祐覚代 弘法大師千二百年法要記念
鐘撞堂兼山門改修梵鐘鋳造」

●「昭和五十三年十月智山代 歓喜寺歴代先師尊霊墓誌建立」

●「昭和五十九年三月智山代 弘法大師千百五十年御遠忌記念 弘法大師像建立」
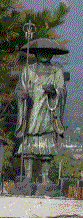
●「昭和六十三年十二月 智山代 本堂新築」
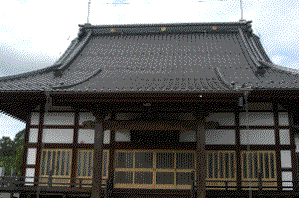
●「平成四年十一月智峰代 興教大師八百五十年御遠忌記念 六地蔵建立」
註記:「六(ろく)地(じ)蔵(ぞう)」とは、六道において衆生の苦しみを救うという六種の地蔵菩
薩。
地(じ)獄(ごく)道(どう)を救う檀陀(だんだ)、餓(が)鬼(き)道(どう)を救う宝(ほう)珠(じゆ)、
畜(ちく)生(しよう)道(どう)を救う宝印(ほういん)、修(しゆ)羅(ら)道(どう)を救う持(じ)地
(ち)、人道(にんどう)を救う除蓋障(じよがいしよう)、天(てん)道(どう)を救う日(につ)光(こう)
の各地蔵の総称。
●「平成二十六年七月、東日本大震災における除染仮置き場(銀山)工事の際に出土した地蔵菩薩
石像六体が、除染工事業者の依頼を受け、歓喜寺に町内の安穏を祈願し『子安じぞう』として安
置。」

●「補陀落山山門前に仁王 安置」
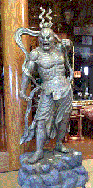
密迹金剛力士(みつしやくこんごうりきし)と 「あ」

那羅延堅固王(ならえんけんごおう) 「うん」
「災害防除、伽藍安穏・寺檀繁栄」を祈願し、歓喜寺に勧請。
|
|
|

|