真言宗豊山派
補陀洛山善明院歓喜寺
| 歓喜寺の境内に祀られる宝物
●稲 村 ふ か 報 恩 記 念 碑

天保十年(一八三九)三月十日
生北半田渡辺半七の二女、稲村長吉ノ養女トナル。北半田字御免町の長屋に独居し昭和五年(一
九三〇)三月八日九十二歳の天寿を全う。
産婆として献身的に村民に貢献したことの功に報い永くこれを子孫に伝えるため、大正十四年
(一九二五)に菩提寺に報恩記念の碑を建立した。
●観 音 堂(東 日 本 大 震 災 により被 災 し、智 峰 代 に 観 音 堂 解体。)

本 尊 観 世 音 菩 薩 は 本堂 に 安置してある。

聖観世音菩薩立像 金仏の由来註
記:言い伝えによると、昔 或る篤信の大檀那であった渡邊家に遊行僧が立ち寄り、供養の接待
のお礼にと念持仏の聖観世音菩薩を一家の護持安泰のためにと安置して、去った。その後、歓喜寺
観音堂にお祀りしたところ、観世音菩薩の効験・利益あらたかなるものがあり、ご縁日には参拝者
が長蛇の列をなしたと伝わる。
●十三夜塔 寛政五年(一七九二)、安政四年(一八五七)の石碑が祀られている。
「十三夜」とは、元々、収穫を行っている真っ只中である旧暦の九月十三日に行うもので、秋の
収穫のお祭として根付いたのではないかと言われている。
●二十三夜塔 宝暦十二年(一七六二)天明二年(一七八二)の石碑が祀られている。
「二十三夜」とは、二十三夜の月は、勢(せい)至(し)菩(ぼ)薩(さつ)の化身と考えられており、
勢至菩薩は阿弥陀如来の脇侍を勤める菩薩様で知恵を司る仏様で、二十三夜に勢至菩薩を念ずれば
万行の罪が滅するという信仰があり、「二十三夜待ち」はこの二十三夜の月の出を待ち勢至菩薩を
祭る行事である。
●六角屋根の「東(あずま)屋(や)」にはこの「月待信仰(つきまちしんこう)」を祈念して『月待堂
(つきまちどう)』と銘々している。
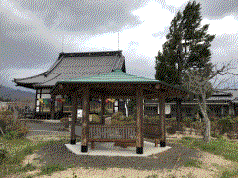
●弁(べん)財(ざい)天(てん)の石碑 宝暦三年(一七五三)文化十四年(一八一七)の石碑が祀ら
れている。
「弁財天」とは、貧困を救い財物を与える天女で、七福神の一人として知られるが、日本におい
ては古くから信仰されている。もともとはインドの豊穣の女神サラスバティである。
●金(こん)毘(ぴ)羅(ら)大(だい)権(ごん)現(げん)の石碑 天保八年(一八三七)の石碑が祀られ
ている。
「金(こん)毘(ぴ)羅(ら)大(だい)権(ごん)現(げん)」とは、仏教
の神に由来する金毘羅神(くびらしん)の信仰。一般には、讃岐の金毘羅大権現(香川県琴平町の金
(こ)刀(と)比(ひ)羅(ら)宮(ぐう)を崇敬する信仰。
●手水舎
「洗心」ちょうずや【手水舎】

神社・寺院の前に設けられた手水所の建物。四方を吹き抜けにして、四本の隅柱の上に軒深い屋根
をかけ、内に水盤・水槽を備える。てみずや。
●江戸期から歓喜寺ではお施餓鬼の供養が奉修されていた。その時に掲げられた五如来幡
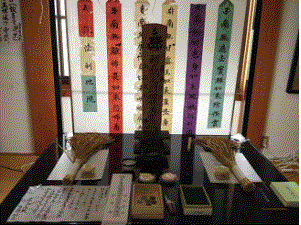 |
|
|

|